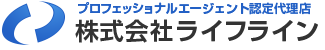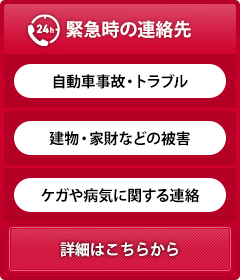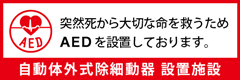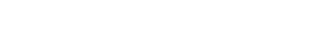月間ニュースレター

2014年1月号 新年のご挨拶

旧年中は一方ならぬご厚情を賜り誠にありがとうございました。
皆さまのお陰を持ちまして、弊社は無事新春を迎えることができました。
感謝の気持ちで一杯でございます。
さて、安倍総理の経済政策のおかげでしょうか、景気も上向きに感じられてきました。
忘年会に並んで、新年会の予定も増えているそうです。
しかし、新年度4月からは消費税が8%に! 月々の家計に大きく影響が出てきそうです。
新春早々ですが、毎月の支出である保険全般を見直すことが必要になってきます。
弊社では、本年もお客さまの『生活=ライフ』を守るために、ライフプランを含めて総合的な保険相談を行っております。より一層お客さま目線でのご相談を行ってまいりますのでいつでもお気軽にご来店ください。
最後に、皆々様のご健勝と御多幸を心よりお祈り申し上げて新年の挨拶とさせていただきます。

株式会社ライフライン 社員一同

2013年12月号 地震・津波・風水害から家族と財産を守るために
防災対策は家族の決まり事が大切

豪雨による土砂崩れや竜巻、断続する地震など、今年も各地で自然災害が発生しました。年末になってこのような話をさせて頂くのは、大掃除を行う際に一緒に防災の準備・点検を行ってもらいたいと思ったからです。自然災害が発生した場合、家の中にいるからといって安全安心とは言えません。タンスや冷蔵庫など家具が転倒・落下したことで下敷きになったり、避難経路を塞がれて逃げ遅れたりすることが多いというのです。特に高齢者の方や小さなお子さんがいるご家庭では転倒・落下の対策が必要になります。ホームセンターに家具の転倒防止対策品が300円(L型金具)から用意されていますので年末の買い出しの際に購入されてはいかがでしょう。たった数千円の防災対策=命を守ることができるのですから。
| 固定方法 | 価格の目安 |
|---|---|
|
L型金具で固定する
|
300~1,000円
|
|
ベルト式、チェーン式
|
1,000~2,000円
|
|
ストッパー式
|
1,000~2,001円
|
|
ポール式
|
5,000~7,000円
|

防災グッズはどこまで準備する?
防災グッズや非常用食料など、災害に備えて一体何を準備したら良いのか? 食料や水は何日分用意すればいいのか? 総務省消防庁のサイトに非常時に最低限必要な防災グッズを記載されています。準備リストとして役立てください。最低限の準備内容ですので、まずはご自宅にあるか確認してみてください。
■『非常時に最低限必要な防災グッズ』
□印鑑 □貯金通帳 □現金 □救急箱 □懐中電灯 □ろうそく □ライター □缶切り □ナイフ □手袋(軍手) □哺乳瓶 □衣類 □ラジオ □電池 □ヘルメット □防災頭巾 □水 □食品
総務省消防庁のサイト http://www.fdma.go.jp/html/life/sack.html
ライフラインが止まった場合の準備は?

災害が発生して困るのは電気・水道・ガス等のライフラインの途絶です。経験したことのない不便で不安な生活が始まります。苦難を乗り越えるためには普段からの備蓄がものをいいます。食料の準備は3日分と言われていますが、実は優先順位としては最後の方なのです。水があれば人間は生きていけますからね。これまでの自然災害において、食料不足で亡くなった方はいないそうですし、ライフラインが停止しても数日内に救援物資が届くからです。 そのため、防災グッズは生命の危険を軽減するものを用意し、次に家屋が危険状態になった場合に避難に役立つものを用意します。また避難所生活が長期になる場合に備えて、健康維持のためのものを用意しておくと良いそうです。
市販の非常用持ち出し袋に自分の必要なものを入れて、その家独自の防災グッズを揃える方法だと手軽に行えますね。下記に役立ちそうなグッズの詳細や注意点を記しておきますので、『非常時に最低限必要な防災グッズ』に加えて準備してください。
災害の時には水がストップして水洗トイレは非常に困ります。また避難場所でも不足することもあります。そこで便利なのが簡易トイレ。消臭剤で排泄物の臭いが軽減されるタイプや、吸収剤で固めるタイプもあります。一つあると緊急時に役立ちます。
■さらに用意しておきたい防災グッズ
医薬品:
常備薬、三角巾、包帯、ガーゼ、脱脂、ばんそうこう、はさみ、ピンセット、消毒薬、整腸剤、持病のある方はその病気のための薬(薬品名のメモも)※小児、高齢者のいる家庭は別途必需品を用意
衣類:
重ね着の出来る衣類、防寒具、毛布、下着類、靴下、軍手、雨具、カイロ
避難所用グッズ:
着替え、毛布、布団、寝袋、タオル、ティッシュ、ウェットティッシュ、ビニール袋、オムツ・生理用品、筆記具(油性)、食器類、スプーン
避難・救助用品:
笛、コンパス、ナイフ、ロープ、懐中電灯、シャベル、バール、ノコギリ、ハンマー等の工具
役立つ日用品:
布粘着テープ(油性マジックを使ってメモに使用。ガラスの破片の除去に利用)、ラップ(水不足の時に食器に使用、保存用に使える)、梱包用ヒモ、風呂敷、ダンボール、簡易トイ
飲料水:
1人1日3リットルが目安(家族3人で2リットルペットボトル12本~18本用意:飲用のみで3~4日分あれば安心)
非常食:
保存期間が長く火を通さず食べられる食品(レトルト、インスタント、クラッカー、缶詰など安価な食を貯めておいて古くなったら消費する)保存可能期間2年~5年が理想
電気の確保はマイカーで行える
災害時には停電して電気が使えなくなります。電話、インターネット、そして様々なアプリで役立つスマートフォンも電源が無くなればただの物体です。現代では電気がないと生活に困ることが多いのです。
停電に備えて電池を用意するのは当然ですが、自分の車があれば、DC/ACインバータを利用して家電製品を使うことができます。シガーライターに差し込めば携帯電話・スマートフォンも充電できます。その際エンジンをかけて充電を行わないと1時間程でバッテリー上がりを起こしてしまいますので注意しましょう。余談ですが、新潟の中越地震の際は復旧に時間がかかり、ガソリンエンジン式の発電機や投光器が本当に役立ったそうです。高額なため誰もが準備できるものではないですが覚えておくと良さそうです。
171 災害用伝言ダイヤルで安否を録音

地震や大雨などの災害が発生した場合、被災地に電話が集中してつながりにくくなります。そこで覚えておいて欲しいのが『171』の災害用伝言ダイヤルです。自宅の一般電話の番号をキーにして、被災地外の家族や親戚、知人などに無事を知らせることができるようにするものです。使い方は簡単で、音声従って30秒間の音声録音ができます。再生も電話番号をキーに行えます。
さらに道路も寸断されてしまうと、仕事中や学校へ行っている子供さんと離れ離れになることも考えられます。いわゆる帰宅困難です。車で動くのは危険ですし、動けたとしても大渋滞によって身動きが取れなくなります。電話もネットも通じず安否確認すらできません。そんな非常事態時の連絡の取り方、帰宅方法、そして最終的な集合場所の取り決めも家族みんなで行っておきましょう。
家族や親族が集まる機会が多い年末年始こそ、家族間の取り決めを確認致しましょう。
自然災害を乗り越えるために『保険』の確認を
大災害が発生して生命が助かったとしても、家屋の損壊、自動車の損害など財産への被害を修復しなくてはなりません。被害状況によっては家屋の建て替えで何千万円の出費となることも…。火災保険や自動車保険の加入の仕方で自己負担なく保険金で元通りに修復することができます。災害が起きてからでは遅いのが保険。ちょっとした特約の設定で保険金が出る、出ないかが分かれます。
年末年始の準備で忙しいとは思いますが、防災グッズの購入と併せて是非ライフラインへお立ち寄りください。無料で災害に関しての保険の点検をさせて頂きます。

2013年8月号 火災保険について
昔に加入したからといっても安心できない…。
最新の火災保険は我々をしっかり守ってくれます
今年の夏は猛暑と集中豪雨と大変な夏を迎えておりますが、皆さまは元気にお過ごしでしょうか。
また、台風・豪雨によって被災された方々には、心よりお見舞い申し上げます。
さて、今回のお話は火災保険の正しい入り方についてです。
火災保険と言えば、火事になった時に保険金が出るだけ…、と考えている方が多いようですが、実は補償の範囲は10通り(建物対象)と幅広いのです。下の表を見ると、この夏猛威をふるった集中豪雨による水災も含まれています。
【火災保険の補償内容一覧】
- 火災
- 落雷
- 破裂・爆発
- 風災、雹災、雪災
- 水災
- 建物外部からの物体の落下・飛来・衝突
- 漏水などによる水濡れ
- 騒擾・集団行動等に伴う暴力行為
- 盗難による盗取・損傷・汚損
- 不測かつ突発的な事故(破損・汚損)
自宅を購入した際に火災保険に加入されている方が大半ですが、その内容についてきちんと理解して加入されているでしょうか? もしくは補償内容を覚えていらっしゃいますでしょうか?
と言うのも、つい先日ある有名なお寺の火災保険を点検させて頂いたところ、重大な補償漏れを発見したからなのです。火災保険の対象として『基礎工事』が含まれていませんでした。これは大変です。もし全焼して基礎の再建が必要になっても基礎工事分の保険金が出ません。つまり建て直すには基礎工事分の何百万~何千万円が自腹になるのです。
そのお寺は文化財に指定されるほどで、寺社専門の代理店が管理していました。ただ過去にうっかり設計ミスした保険内容を疑わず、そのまま契約更新を繰り返していたのです。お互いに信用していても、保険内容の確認はやはり襟を正して慎重に行わなければいけません。私も良い教訓になりました。
内容が分からなければ
安心することはできません
その意味でも、火災保険に入ったけれども随分前で覚えていないな…、というお家の場合はぜひ点検することをオススメします。例えば住宅ローン30年を組んでいるケースですと、火災保険の期間も30年にしています。一括で保険料を支払っていると、点検する機会はほぼありません。事故が起きてみて、対象となる補償に入っていなかった!? といった悲劇にならないようにライフラインの専門スタッフがお手伝いします。
火災保険の点検は保険証券をお持ちいただければ無料で行います。事前にお電話頂けましたら待ち時間なく点検可能です。この夏休みにどうぞご来店ください。
保険金額の設定方法次第で
1、000万円損することもある
そしてもう一つ大事なポイントがあります。保険金額の設定方法です。最近の火災保険では「新価」を基準に保険金を設定することが主流になっています。実は「新価」でないと十分な補償が受けられないからです。
「新価」とは同等のものを新たに建築あるいは購入するために必要な金額をいいます。昔の火災保険は「時価」で設定したケースが多く、「経過年数による価値の減少や消耗分」を差し引いた現在の価値が金額となります。そのため購入した際より金額は低くなります。
例えば、20年前に2、000万円で購入した建物が全焼した場合、同じように建て直すには2、500万円が必要とするケースでは、
「新価」では 2、500万円が出ます。しかし「時価」では経過年数と消耗分を引いた金額の1、500万円しか出ません。
保険金の設定方式だけで1、000万円差が出るのですから、これも点検しなくてはいけない項目ですね。

多く掛けても、少なく掛けても損をする
保険金額は適切に計算してもらおう
火災保のお勉強の最後として、保険金を実際にいくらに設定するかについてお話しします。
火災保険は建物と家財にかける保険です。建物や家財それぞれ別々にいくら?という形で加入しますが、保険金額の設定次第で十分な補償を得ることができなくなることがあります。
心配だからといって、2、000万円の建物に2倍の4、000万円の保険金を設定しても、被害に遭ったのが全損で2、000万円でしたら2、000万円しか出ません。これを超過保険と言って、保険料を倍額払って保険料の無駄になります。また保険料は返金されません。
反対に、2、000万円の建物に対して保険金を半分の1、000万円に設定した場合、損害額が500万円としても実際に出るのは比例てん補で減額されて、312.5万円しか保険金が出ません。
いずれにしても、保険金額の設定は専門家に算出してもらうのが安心です。正確に設定しないと損をするのは皆さま自身ですからね。
火災保険はお家の守護神
覚えておいて欲しい保険金が出るケース
では、火災保険はどんな時に補償されるのか? 勘違いしやすい例から説明しましょう。
①自宅で車庫入れをした時、誤って車庫の柱に激突して自動車も車庫も修理が必要になった場合、車の修理代は車両保険に加入していれば出ますが、車庫の修理代は火災保険から出るのです。「建物外部からの物体の落下・飛来・衝突」によって、自動車保険ではカバーできない部分を補償してくれるのです。この事故、結構ありそうですよね?
②小さいお子さんがテレビのリモコンを投げてしまいリモコンがテレビを直撃。液晶部分が割れてしまい、液晶交換修理のために15万円かかることになりました。この修理費用も「不測かつ突発的な事故(破損・汚損)」によって保険金(自己負担分1万円あり)が出るのです。
③外から石が飛んできて窓ガラスが割れてしまった場合も、「建物外部からの物体の落下・飛来・衝突」によってガラスを直すことが出来ます。
④自宅のアンテナに雷が落ちて、アンテナからの過電流によりテレビが故障。そのテレビを買い替えた場合も「落雷」の補償により保険金が出ます。
⑤夜、駅から徒歩で自宅に向かって歩いていたら、後ろから走ってきたバイクにバッグをひったくられてしまった。バッグの中には、現金5万円が入ったお財布が入っていた場合、携行品損害特約を付帯していると補償してくれます。
⑥友達の結婚式に向かって、駅の階段を降りていたら足を踏み外して転倒。ケガはなかったのですが、着ていた結婚式用の高級服がバサっと破れた場合、これも携行品損害特約を付帯していると修理代を補償してくれます。
外や意外! 火災保険はとても便利な補償が盛り沢山です。火災保険というから分かりにくいのかもしれませんが、大切なお家を守ってくれる総合的な保険と考えて、内容を正確に理解して加入するべきです。内容が分かっていれば安心安泰。この機会にライフラインで火災保険の点検を行ってみてはいかがでしょうか。

2013年7月号 なぜ海外旅行保険が必要なのか?
祝 顧客満足度ナンバー1になりました!!
損保ジャパン
新・海外旅行保険 【off!(オフ)】
なぜ海外旅行保険が必要なのか?
みなさんこんにちは。
今年の夏は猛暑と予測されていますが、皆さま元気にお過ごしでしょうか?円安傾向とは言え、夏休みは家族や友人と海外旅行に出かける最大のチャンです。そこで! 楽しい旅行のために、渡航前の最後の準備となる海外旅行保険についてお話しします。

なぜ、渡航する度に海外旅行保険が必要なのか? その理由は以下の通りです。
①海外での医療費がとても高額だから
②盗難や紛失などのトラブルに遭った時にサポートしてくれるため
③海外で事故を起こしてした時に対処してくれるため
分かりやすくするためにこの3つに大別してみましたが、特に医療費などは考えられない程の高額な費用がかかります。事故の賠償金を支払えないことで帰国後も多額な借金を抱えて生活することにもなりかねません。では、具体的にどんな時に海外旅行保険は役立つのか? 支払いがあった事例を紹介しましょう。
【事例1】
救急車も有料! 盲腸が240万円~50万円

国や地域によりますが、もし盲腸で手術・入院した場合、アメリカ・ハワイでは約240万円もの費用がかかると言われています。平均的にはヨーロッパエリアは100万円~150万円程度が相場。近隣のソウルや北京などのアジアエリアは約50万円程度と聞いています。
日本だと約40万円。このうち3割負担の12万円を病院で支払いますが、高額療養費制度により最終的な自己負担は約8万円です。凄い金額差ですよね。
また救急車は有料で、アメリカのニューヨークの場合、約20万円+運賃(走行距離)となっています。有料の医療タクシーという訳です。
【事例2】
ヘリで捜索 1回200万円以上

海外ハイキングも隠れたブームで、スイスやカナダに年配者の方が多く訪れているようです。そんな楽しいハイキング中、天候が急に悪化して遭難しヘリコプターで捜索されて救出劇に…。または綺麗な珊瑚礁の海をボートで出かけたら、潮流流されて遭難し船とヘリコプターで捜索されて救出劇に…。この場合、ヘリコプターの一日の捜索費用は200万円以上と言われています。
【事例3】
お湯をあふれさせて1,200万円

4つ星クラスのホテルに泊まった際、うっかりバスタブのお湯をあふれさせてしまい、階下と周囲の部屋を使用できなくしてしまいました。そのたため、ホテル側から損害の賠償として約1,200万円を請求されましたが保険金が支払われました。
【事例4】
貴重品が盗難に! 17万円

損保ジャパンのHPにも掲載されていますが、コペンハーゲンにて買い物中の女性がリュックサックを開けられて貴重品を盗まれました。総額約17万円を携行品損害として保険金が支払われました。
現金不要!「キャッシュレス治療サービス」で
現地で面倒な手続きが不要
海外で病気やケガで治療を受けた場合、【off!(オフ)】では、治療費が損保ジャパンから病院に直接支払われる仕組みがあります。だから、現地で現金を支払う必要がないのです。本当に便利ですね~。またこの「キャッシュレス治療サービス」を利用することは損保ジャパン・メディカルヘルプラインの担当者が現地の病院に連絡してくれますから、外国語を話せなくても大丈夫です。
24時間 日本語OK
困った時にはいつでも相談できます
もし海外でケガや病気になって困った時、24時間日本語で対応してくれる海外トラベルサポートが海外旅行保険にはついています。病状の説明や治療の説明について電話で通訳をしてくれます。パスポートを紛失した時や、クレジットカードを紛失した時にも各方面の手続き方法について案内してくれます。困った時に旅のコンシェルジュとして機能してくれます。
オリコン調査
新・海外旅行保険 【off!(オフ)】 がNo.1
今回、ランキングを調査する老舗オリコンにおいて、損保ジャパンの新・海外旅行保険 【off!(オフ)】が顧客満足度ランキングの総合1位に選ばれました。5、000人対象の調査だそうで、素晴らしいことに! 調査項目8つの内、7項目で1位という快挙を達成しました。新聞でもそのことが紹介されています。記事中のお客さまの声を紹介しますと。
「ネットで簡単に加入できて、オーダーメイドで設計できるので不要な保険料を節減できた」(50代男性)
「電話もスムーズにつながって、対応も迅速丁寧」(30代男性)
さらにはインターネットで加入すると保険料が40%割引になることも人気の理由でした。この保険を人に薦めたくないというネガティブ出現率という数値があるのですが、これも平均1.9%とダントツの好評価となっています。
事故が起きてからは遅い
楽しい旅行のために安心の準備を
海外旅行保険事故データによると、2011年は28人に1人が何らかの事故に遭っているそうです。1996年の調査開始以来、過去最高を記録しています。異文化交流は楽しいことですが、万が一トラブルが起きてからでは遅いものです。それが言葉の通じない海外となれば尚更です。
今回ランキング1位になった 損保ジャパンの新・海外旅行保険 【off!(オフ)】 はライフラインのホームページから保険の設計が行えて、そのまま加入することができます。是非クリックしてみてください。
何か分からないことがあれば、いつも通りライフラインへお問い合わせください。懇切丁寧にご説明します。

2013年4月号 「リスク」について考えてみましょう。
 皆さん こんにちは!!
皆さん こんにちは!!
いかがお過ごしですか?3月中旬から気温が上昇して、暖かいを通り越して暑くなってきましたね。もう夏日になったところも有ります。暖かくなるにつれ、今年は本当に花粉がすごいです。私はいままで花粉症ではなかったのですが、今年は眼がかゆくてたまりません。いよいよ4月、新年度の始まりです。また新たな気持ちで頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。
我々の周りにはいろいろな「リスク」が存在します。どのような「リスク」に備えたらいいのか、お客さまの安全と安心をお守りするには私達はどのような提案をしたらいいのか?保険代理店として「リスクカウンセラー」「ライフカウンセラー」として、お客さまに有益な情報提供ができるかが重要な業務と考えています。今月はこの様々な「リスク」について考えてみましょう。
㈱損害保険ジャパン日本興亜とNKSJひまわり生命保険㈱からデータからみる保険のこと「損害保険・生命保険データブック」[活用ガイド]という小冊子が刊行されました。この小冊子は「くるま」「ケガ」「いのち・入院」「介護・老後」「住まい」のジャンル別に「リスク」に関するデータが判りやすく簡潔に記載されています。この小冊子の内容を抜粋して紹介させていただきます。
まず「くるま」に関するデータです。<45秒に1件の割合で交通事故が発生・・><人身事故で3億円・物損事故で2億円を超える賠償も・・>等。自動車事故については「リスク」が顕在化しており、対人・対物賠償保険金額の無制限化率もかなり高くなっています。問題は「自転車」の事故が増えており、「個人賠償保険」の提案を今後もお勧めしていきたいと思います。
次は「ケガ」ですが、<日常生活のケガや旅行中のトラブル・・・>について、特に海外旅行中の「リスク」についてのデータが詳しく載っています。海外での病気や治療費は高額になるという事例が紹介されています。海外旅行保険に加入していても、既往症の病気については保険金支払いの対象外になってしまう事がありますので説明が必要だと思います。
「いのち・入院」については主に死亡原因や入院について紹介しています。<死因はがん・心疾患・脳血管疾患で全体の半数を占めます><入院費は経済的にも大きな負担です>等。入院費の健康保険でカバーされない差額ベット代等の自己負担についての説明もありますので参考となります。
「介護・老後」はかなりセンセーショナルです。<2040年には人口の3分の1が65歳以上・・><20歳代から50歳代のおよそ9割の人が老後の生活を心配している>等。今後ますます要介護者は増加すると思いますし、年金については支給額や支給開始年齢が悪化すると思います。また、将来の年金額のシュミレーションもできます。この分野は早めの準備が必要ですね。
最後に「住まい」です。<火災保険は火災以外の事故でも多くの事故件数が有ります> 近頃は、爆弾低気圧による水災・風災・雪災等の被害や大きな竜巻等による被害が大型化しています。また3.11以降「地震保険」は加入率が上昇しています。ただし、3月末に損保料率機構が地震保険料率を全国平均で15.5%引き上げる届出を行いました。2014年7月に値上げは実施される予定です。でも地震保険は必要ですね。
この小冊子をご希望の方は、弊社までお申し出ください。至急お送りいたします。なお、この小冊子の最終ページのチェックリストはかなり優れ物で、本当に必要な補償(保障)が揃っているか自分でチェックできます。


2013年3月号 「睡眠」について考えてみましょう。
 皆さん こんにちは!! いかがお過ごしですか。
皆さん こんにちは!! いかがお過ごしですか。
3月に入って陽射しがようやく和らいできました。しかし、暖かくなってくると花粉が本格的に飛び出し始めます。花粉症の人はつらい時期になりますね。特に今年は、黄砂とPM2.5が中国から来襲すると大騒ぎです。中国では、大気汚染がものすごいため、日本製の空気清浄機がバカ売れだそうです。日本製品ボイコットはどうしたのかな?という感じです。
「春眠暁を覚えず」(春の夜はまことに眠り心地がいいので朝が来たことにも気付かずつい寝てしまう)という漢詩にもあるとおり、春は寝るには大変良い季節です。しかし、現代では「睡眠障害」の人が増加し、社会問題となっています。
今月は「睡眠」について考えてみましょう。
「睡眠障害」は過眠症を含む睡眠の不具合の総称で、寝付けない日が続き、日中の活動に支障が生じると「不眠症」と診断される。文科省の調査では日本人の成人の約20%が何らかの「睡眠障害」を抱え、そのうちの半数が不眠で悩んでいるそうです。
「睡眠不足で疲れが取れないよ」とよく聞きますが、実は体のための睡眠は全体の約1/5、ほとんどが脳の為の睡眠と言われています。人の体で睡眠不足に弱いのは大脳です。少しくらいの睡眠不足で筋肉が衰えることはないが、大脳は細胞の一部が壊れたり適正な指令が出せなくなります。脳は自らの細胞復活を図るため、言葉を替えると生きるために睡眠を取るのです。
脳は働き過ぎるとホルモンの使いカスがたまります。この物質は疲労物質と呼ばれますが、睡眠によって疲労物質を取り除き、脳を休息させることは人間が心身ともに健康な状態を保つために必要です。 また、いくら寝ても疲れが取れないというのは質の良い睡眠が取れていないということです。睡眠の質はその時間の長さより内容で決まります。睡眠には浅い眠りの「レム睡眠」と深い眠りの「ノンレム睡眠」があります。一晩の睡眠中にレム睡眠とノンレム睡眠を90分周期で4~5回繰り返します。
また、いくら寝ても疲れが取れないというのは質の良い睡眠が取れていないということです。睡眠の質はその時間の長さより内容で決まります。睡眠には浅い眠りの「レム睡眠」と深い眠りの「ノンレム睡眠」があります。一晩の睡眠中にレム睡眠とノンレム睡眠を90分周期で4~5回繰り返します。
「レム睡眠」とは、脳は起きていても体は眠っている状態の事をいいます。目覚めの準備段階でもあるため、レム睡眠の時に目覚めるとすっきりします。「ノンレム睡眠」とは、脳が眠っている状態の事をいいます。入眠直後にあらわれ、夢はほとんどみず、体を支える筋肉は働いています。大脳が最も休まる1回目と2回目のノンレム睡眠時に、いかにぐっすり眠れるかどうかで疲労の回復が違います。居眠りのほとんどはノンレム睡眠といわれ、昼休みなどに10分~20分眠るだけでもスッキリするのは脳が休息するからです。
不眠症には主に4種類あると言われています。翌日の仕事等の予定が気になったり、いやな事を言われたりして緊張が続き、寝付くまでに30分から1時間以上かかる場合の「入眠障害」。頻尿や睡眠時無呼吸症候群などの病気が原因となることが多い、夜中に何度も目が覚める「中途覚醒」。加齢とともに体内時計が進みやすくなり、睡眠が朝方になって予定より早く目が覚め、その後眠れない「早朝覚醒」。睡眠時間は十分でも眠りが浅く、起きた時に疲れやだるさが残っている「熟眠障害」。また、不眠は睡眠不足とは根本的に違いますので注意して下さい。
薬剤性過眠・うつ病・長時間睡眠者・睡眠不足症候群・ナルコシプレー・特発性過眠症・睡眠時無呼吸症候群・むずむず足症候群・周期性四肢運動障害・月経随伴睡眠障害・睡眠相後退症候群等症状によりいろいろな病気があります。眠れない・寝つきが悪い・眠りが浅い等眠れない夜は誰にでも有ります。不眠が長く続いたり、他の症状があるときは上記のような病気かもしれません。社会生活に支障が出るほどひどい時は、早めに睡眠障害の専門医療機関を受診しましょう。
弊社でも従業員に「睡眠時無呼吸症候群」を患った人がいます。現在は治療をして大分改善していますが、病気中は会議で居眠りをしたり、居眠り運転で事故を起こしたり大変でした。この病気でも加入できるケースの生命保険(無選択型終身保険・がん保険・限定告知型医療保険)も有りますので、詳細についてはご相談して下さい。
 不眠対策の核となる対応は、毎日の規則正しい生活が一番です。生活のリズムを崩さないよう気を付け、ストレスの原因を取り除き、太陽の光を浴びて、適度な運動を心がけましょう。素敵な眠りは翌日の活力を作り出します。
不眠対策の核となる対応は、毎日の規則正しい生活が一番です。生活のリズムを崩さないよう気を付け、ストレスの原因を取り除き、太陽の光を浴びて、適度な運動を心がけましょう。素敵な眠りは翌日の活力を作り出します。
健康の為にも「快眠」は絶対必要ですね。

2013年2月号 「アルコールの害」について考えてみましょう。
皆 さんこんにちは!!正月もあっと言う間に終わり、2月となりました。しかし、本当に寒いですね。年末から始まった寒波は依然衰えておらず、2月の前半までは低温傾向が続きそうです。「エルニーニョ現象」になると暖冬、冷夏になりやすく、現在の日本のように「ラニーニャ現象」の影響下では冬は寒くなり、夏は猛暑になる確率が高いそうです。寒いのも暑いのもほどほどが良いですね。
さんこんにちは!!正月もあっと言う間に終わり、2月となりました。しかし、本当に寒いですね。年末から始まった寒波は依然衰えておらず、2月の前半までは低温傾向が続きそうです。「エルニーニョ現象」になると暖冬、冷夏になりやすく、現在の日本のように「ラニーニャ現象」の影響下では冬は寒くなり、夏は猛暑になる確率が高いそうです。寒いのも暑いのもほどほどが良いですね。
さて、年末年始は忘年会、新年会とお酒を飲む機会が多かったと思います。昔から「酒は百薬の長」と言われてきました。しかし、アルコールは、我々日本人が考えてえている以上に健康に悪影響を与えているようです。
今月は「アルコールの害」について考えてみましょう。
お酒を飲むと、アルコールは体内で発がん物質であるホルムアルデヒドによく似た「アセドアルデヒド」に分解されます。この物質の量がちょっと多くなるとフラッシュ反応が起きます。顔が赤くなったり、心臓がバクバクしたり、頭痛がしたり、吐き気を催したりする人は注意が必要です。
 白人にはこの物質を分解する酵素(アセトアルデヒド脱水素酵素)の遺伝子に変異性がないから、お酒で顔が赤くなる人はまずいません。東洋人の約3~4割は、アセトアルデヒド脱水酵素の遺伝子に変異が認められます。この人たちは、お酒を飲み過ぎると分解しきれずに「アセトアルデヒド」が体内にたまり、発がんの原因となるそうです。
白人にはこの物質を分解する酵素(アセトアルデヒド脱水素酵素)の遺伝子に変異性がないから、お酒で顔が赤くなる人はまずいません。東洋人の約3~4割は、アセトアルデヒド脱水酵素の遺伝子に変異が認められます。この人たちは、お酒を飲み過ぎると分解しきれずに「アセトアルデヒド」が体内にたまり、発がんの原因となるそうです。
欧米では飲酒(アルコール)によるがんのリスクに関してはあまり問題になっていません。しかし、日本ではアルコールを分解できる体質の人が、白人に比べて少ないためお酒の害を無視することはできません。
飲酒関連の死亡率は飲酒量で増加します。月に1~3日程度飲む人を基準とすると、2日に1合程度以上の飲酒習慣のある人の死亡率は高くなります。がんの種類として、飲んだお酒が最初に通過する部位(口腔・喉頭・咽頭・食道など)と胃から体に吸収されたアルコールを分解する肝臓に発生するものが増加します。たとえば、毎日日本酒を4合飲む日本男性は、大腸がんになる危険が3倍になります。特にタバコを吸いながら深酒をするのは自殺行為で、がん発生率は大幅に上昇するそうです。
「酒は百薬の長」は、がんには当てはまらないようです。また、酒飲みは高血圧・脳卒中・肝硬変・アルコール依存症など他の重大な病気の原因となります。毎日飲むなら量は1日平均で日本酒1合程度まで、アルコール量で30mlまでに押さえましょう。また、週に1~2回の休肝日を作りましょう。
適度のお酒にはリラックスでき、交感神経の緊張をゆるめ、日頃のストレスが発散できる効用があります。お酒を美味しく飲んだ夜は、ぐっすり眠れて、すっきりしたという経験がありませんか。また、全身の血行を良くして、手足を温めます。腎臓の血行も良くなる為に、尿の量も増え、老廃物を体外に排出することもできます。このように「酒は百薬の長」といわれる作用もあります。
ただし、寝酒には注意が必要です。依存性からどんどん量が増え、過度の飲酒は覚醒作用がありますので、かえって眠れなくなっていきます。また、薬物依存症と同様にアルコールに対して依存が強くなっていくと「アルコール依存症」という病気になってしまいます。「アルコール依存症」と「アルコール中毒」は厳密には違いますが、どちらも生命保険加入に際して引き受けは難しいそうです。
適量のお酒は本当に楽しいものです。体を壊さないようおいしいお酒をいただく事は生活を豊かにしてくれます。
さあ、今夜も楽しいお酒をいただきましょう。

2013年1月号 新年のご挨拶 2013


2012年12月号 「飲酒運転」について
皆 さん こんにちは!すっかり寒くなりましたが、いかがお過ごしですか?私のまわりでも風邪をひいている人が増えています。一年の疲れが出てくる時期ですので、体調には十分注意して下さい。さて、今年も残すところあとわずかとなりました。今月は、年末の忙しさと選挙が重なり本当ににぎやかな月となりそうですね。
さん こんにちは!すっかり寒くなりましたが、いかがお過ごしですか?私のまわりでも風邪をひいている人が増えています。一年の疲れが出てくる時期ですので、体調には十分注意して下さい。さて、今年も残すところあとわずかとなりました。今月は、年末の忙しさと選挙が重なり本当ににぎやかな月となりそうですね。
さて、年末は忘年会等でお酒を飲む機会が増えると思います。いまだに飲酒運転による悲惨な交通事故は、後を絶ちません。今月は「飲酒運転」について考えてみましょう。
「飲酒運転」による死亡事故は、平成14年6月に改正道路交通法により罰則強化されたことで減少し、平成18年9月以降の飲酒運転根絶に対する社会気運の高まりと取締強化、平成19年9月のさらなる罰則強化、21年6月の悪質・危険運転者に対する行政処分強化等により、平成18年以降はさらに減少して、平成22年では平成12年に比較して約5分の1以下になりました。
交通事故死者数はピーク時(昭和45年)には16,765人でしたが、平成23年は4,612人と11年連続で減少しています。しかし、飲酒運転等の悪質運転による事故は依然として厳しいものがあります。平成23年の飲酒運転による死亡者数は13名、負傷者数は218名と、罰則・処分が重くなっても懲りない人が多いですね。

「飲酒運転」とはビールや日本酒などの酒類やアルコールを含む飲食物を摂取し、アルコールを体内に保有した状態で運転する行為です。アルコールは少量でも脳の機能を麻痺させ、安全運転に必要な情報処理能力、注意力、判断力などが低下します。酒に強い人でも低濃度のアルコールで運転操作に影響がみられることが各種調査研究で明らかになっています。飲酒したら絶対に運転はやめましょう。

アルコールの処理にかかる時間は、1単位のアルコールを飲むと、飲み終わってから体内処理におよそ4時間かかります。飲酒して8時間後に勤務したとします。2単位ならまず検出されませんが、3単位だと検出される可能性が高くなります。アルコールの分解処理には、体質・体重・体調・飲み方などによる個人差・性差があり、睡眠中は処理が遅くなります。翌朝まで残るような飲み方はやめましょう。
 万が一飲酒運転事故を起こした場合、「自動車保険」は支払われるでしょうか?自賠責保険、自動車保険の内対人・対物賠償保険等他人を死傷させたり、他人の物を壊した場合には支払われますが、運転者自身の死傷や自分の車については補償されません。 それでは「生命保険」はどうでしょう。「終身保険」や「定期保険」などの死亡保障の生命保険は支払い対象となりますが、「医療保険」の入院給付金や手術給付金等は受け取ることができません。
万が一飲酒運転事故を起こした場合、「自動車保険」は支払われるでしょうか?自賠責保険、自動車保険の内対人・対物賠償保険等他人を死傷させたり、他人の物を壊した場合には支払われますが、運転者自身の死傷や自分の車については補償されません。 それでは「生命保険」はどうでしょう。「終身保険」や「定期保険」などの死亡保障の生命保険は支払い対象となりますが、「医療保険」の入院給付金や手術給付金等は受け取ることができません。
飲酒運転で人身事故を起こした場合、「危険運転致死傷罪」が適用となるケースも有ります。実際に死亡事故の場合、懲役20年の判決を受けた判例も有ります。多額の賠償金(保険で手当てできる場合有り・・・)と自身のケガの治療費、車の修理代、行政処分や刑事罰、社会的制裁による信用失墜や失職など金銭的にも精神的にも追い詰められ、人によってはまさに人生が終わってしまう場合も考えられます。本当に「飲んだら運転しない」を励行しましょう。
今年も「おがわ通信」を愛読していただきありがとうございました。来年も宜しくお願い申し上げます。

2012年11月号 「防衛運転」の一つの方法である「危険予知(予測)運転」について。
 皆さん こんにちは!!
皆さん こんにちは!!
10月中旬から急激に温度が下がり、涼しいを超えて寒 くなってしまいましたね。今年は春の期間も短かったですが、秋の期間も短そうです。秩父路では、毎年恒例の秋の催しが各市町村で開催されるので楽しみです。さて今年も残すところ、あと2カ月となりました。これから 忙しい時期になりますが、体調管理を心がけてがんばりましょう。
先月号では、事故を起こさない為の「防衛運転」について取り上げました。今月は「防衛運転」の一つの方法である「危険予知(予測)運転」について考えてみましょう。
「防衛運転」を考える時必ず出てくるのが、「ハインリッヒの法則」です。1:29:300の法則とも言われており、1件の重大な災害や事故には29件の軽い災害・事故があり、300件のヒヤリ・ハットがあるという法則です。事故にはなっていないヒヤリ・ハットには、さらに多くの不安全な行動と状態があると言われていますが、これらのほとんどは事前に予防することが可能であると考えられています。
ミスや事故を起こすことが許されない医療や航空機の運航の現場では、ハインリッヒの法則が取り入れられ、実践されています。「防衛運転」とは、事故に結びついてしまう恐れのある行動や現象に事前に注意・対処する運転テクニックです。日常の何気ない行動に注意を払うことこそが、重大な事故を防ぐことができるということです。
「防衛運転」とは、事故に遭遇する確率を減らすような走り方を言います。つまり、前を走るドライバーが急ブレーキをかけるかもしれない。(危険予知)そのためには、車間距離を十分に取ろう。(防衛運転)道路わきから子供が飛び出すかもしれない。(危険予知)すぐに停止できるスピードで走ろう。(防衛運転)等々・・・
我々は日常運転で「危険予知」「防衛運転」の行動を実行していますが、自分がどんな運転をしていても他のドライバーや歩行者の過失によって事故に会うことがあります。 しかし、「危険予知」による行動を取ると取らないでは、結果が全然違います。
事故を起こさず、事故に巻き込まれないような運転には、様々な交通状況にひそむ危険を早めに予測し、危険を回避する行動が求められます。この様な危険予測能力を高めることは訓練次第で向上させることができます。それでは下記の例題で「危険予知・予測訓練」をしてみましょう。
*車で住宅街の道路を走行しています。この状況ではどのような危険因子が含まれているでしょう。「考えられる危険要因」を考えてみましょう。(まずは解説を読まないで考えてください)

<危険要因の解説>
1. 前方のT字路から出てくる車・自転車・バイクや人と衝突する危険。
(前方路面┣の標示に注意。この表示はT字路のあることを示している。
対向車のため表示が見ずらいので注意が必要です。)
2. 前方を走行している自転車との接触する危険。
(自転車追い越し時、自転車がふらつく恐れが有り。前方のバイクに気をと
られると路側に寄りすぎることがあり自転車と接触するおそれ)
3. 対向バイクとの衝突危険。
(バイクは駐車車両を避けるため中央寄りを走行してくることが予測できる。
自転車に気が行き過ぎるとバイクと接触する危険が有り)
いかがでしたか?上記はほんの一例ですが、これらの危険要因を取り除く運転が「防衛運転」です。あらためて「危険予知訓練」というと大げさになりますが、私達は運転時にはこの予知・予測をしながら、必ず運転をしていると思います。この予知・予測を怠った時に事故の発生率が高まります。一瞬の気の緩みから事故は発生します。年末は道も混み合いますし、気も急かされます。落ち着いて安全運転をこころがけましょう。
141 ~ 150件 / 全236件